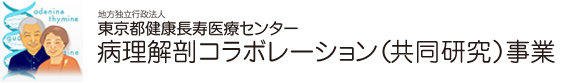HOME > 病理解剖例を用いた共同研究事業一覧 > 病理解剖例を用いた全身動脈の粥状硬化度の加齢による変化、分布、性差について
研究課題名
病理解剖例を用いた全身動脈の粥状硬化度の加齢による変化、分布、性差について
共同研究者
| 氏名 | 所属 | 職名 |
|---|---|---|
| 沢辺元司 | 東京都老人医療センター剖検病理科 | 部長 |
| 濱松晶彦 | 東京都監察医務院 | 医員 |
| 千田宏司 | 大田病院 | 副院長 |
| 原田和昌 | 東京都老人医療センター循環器科 | 部長 |
| 小澤利男 | 東京都老人医療センター | 名誉院長 |
| 田中紀子 | ハーバード大学公衆衛生大学院 | 客員研究員 |
研究内容
年をとると動脈硬化がおこります。動脈硬化は太い動脈でおこる粥状硬化症、中等度の動脈で起こる中膜石灰化症、細動脈硬化に分かれます。中でも粥状硬化症では動脈壁が破壊されて動脈瘤を形成したり、内腔を狭窄して末梢の臓器の虚血・梗塞をおこしたりする重要な血管病である。心臓、脳、下肢の動脈に粥状硬化症がおこると、それぞれ、心筋梗塞、脳梗塞、下肢の壊疸をおこします。動脈は一般に体の深部を通過するため、粥状硬化症の程度を測定するのは困難で、病理解剖においてのみ全身の粥状硬化症の程度を一度に測定することが出来ます。今回、私たちは多数の病理解剖症例を用いて、80歳以上になっても、全身動脈の粥状硬化症が進行すること、90歳以上では性差がなくなることを見つけました。従って、70歳台、80歳台になっても粥状硬化症の進展を予防することが重要と思われました。